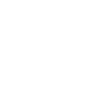道元禅師の禅戒について
師家会副会長・智源寺専門僧堂 堂長
高橋信善
※漢文部分にて本来の記法と異なる部分がありますがご了承ください。
第6章
さて、次には「懺悔滅罪」について考えて参りたいと思います。「禅学大辞典」によれば、「・・・懺悔の様式には衆法懺、対首懺、心念懺の三種の別がある。衆法懺とは重大な罪を四人以上の僧伽に懺悔すること。対首懺とは軽罪を師一人に懺悔すること。心念懺とは微罪を本尊を念じて自ら心に懺悔すること。大乗では理懺と事懺の二儀両懺を説き、実際に行うのは称歎、礼拝、誦経等の事懺である。・・・」とあります。
曹洞宗で懺悔といえば、「修証義」の「懺悔滅罪」が思い浮かびます。
「・・・然あれば誠心を専らにして前佛に懺悔すぺし、恁麼するとき前佛懺悔の功徳力我をの功徳力我を拯いて清浄ならしむ・・・」
とあります。先程の分類によれば、心念懺か事懺になるかと思います。
また、お授戒の第五日目の夜、「懺悔道場」をお努めいただきますが、三師(戒師、教授師、引請師)様が懺悔帳を焼却するときにお唱えするお言葉に
「一切ノ業障海ハ皆ナ從り二妄想一生ズ若シ欲セバ二懺悔セント一者端坐シテ思へニ實相ヲ一衆罪ハ如シ二霜露ノ一慧日能ク消除スト」(普賢経)
のお言葉があります。これは理懺悔になるのではないでしょうか。
このように見てまいりますと、高祖様は理懺と事懺の両懺悔をお説き下されています。しかし、より特色のあるのは理懺(実相懺悔)と言うことが出来ます。以下の三祖鑑智僧璨の懺悔滅罪にも明らかです。
(三祖鑑智僧璨、太祖慧可章)
・・・(慧可)大師、(達磨大師に)継いで玄風を闡き、博く法嗣を求む。北斉の天平二年に到るに一居士有り。年、四十を踰ゆ。名氏を言はず。聿に来り、札を設けて師に問ふて曰く。弟子の身、風恙に纏はる。請ふ、和尚、罪を懺さんことをと。師日く。 罪を将ち来れ。汝がねに懺さんと。居士、良久して云はく。罪を覓むるも得べからずと。師日く。我れ、汝が与に罪を懺し竟んぬ。宜しく佛法僧に依りて住すべしと。日く。今、和尚を見て巳に是れ僧なりと知る。未審し。何をか佛法と名づくと。師日く。是の心は是れ佛なり、是の心は是れ法なり。法と佛は二無し、僧宝も亦然りと。
日く。今日、始めて知る、罪性、内に在らず、外に在らず、中間にも在らざることを。其の心の然るが如く、佛法も二無しと。大師、深く之を器とす。即ち為に剃髪して云はく。是れ吾が宝なり。宜しく僧璨と名づくべしと。
其の年の三月十八日、光福寺に於いて受具す。茲れより疾漸く愈へ、執侍して二載を経。大師乃ち告げて日く。菩提達磨、遠く竺乾より正法眼蔵を以て密に吾れに付す。吾れ今、汝に授く。幷に達磨の信衣、汝、当に守護して断絶せしむること無かるべし。吾が偈を聴けと。日く。本来、地有るに縁り、地に因って種華生ず。本来、種有ること無ければ、華も亦嘗て生せず。
「傳光録」には、
【本則】
第三十祖、鑑智大師、二十九祖に参ず。問いて日く、「弟子の身、風恙に纏わる、請うらくは和尚、罪を懺ぜよ。」祖日く、「罪を将ち来れ、汝の与めに懺ぜん。」師良久して日く、「罪を覚むるに不可得なり。」祖日く、「我れ汝が与めに罪を懺じ竟る、宜しく佛法僧に依りて住すべし。」
【拈提】
其最初参見の時、身、風恙に纏はるといふは癩病なり。然れども祖師に参見せしに、業病※、忽ちに消除せし因縁、別の様子なし。罪性不可得なることを了知し、心法、本清浄なることを学悟す。之に依て佛法に二つなしと聞き、心法加然なりといふ。
実に本来心を識得せんとき、尚ほ死此生彼、差異なし。何に況や罪悪善根の弁別あらんや。之に依て四大五薀終に存せず、皮肉骨髄本より解脱す。故に風恙の病消除し、本来の心現前す。終に第三の祖位に列なる。法要を広く説くに日く、至道無難、唯嫌㨂択と言ふより、言語道断、非古来今と説く。実に是れ内外なく中間なし。何をか択び何をか捨てん。取ることも得ず、捨てることも得ず。既に憎愛なく洞然明白なり。時として欠けたる所なく、物として余る法なし。然も是の如くなりと雖も、子細に参徹して不可得の処を得来り、不思議の際に到りもてゆく。断滅に同ふすることなく、木石に等きことなく、能く空を扣て響を為し、雷を繋いで形を為し、没蹤跡の処に子細に眼を著け、更に蔵身することなくんば好し。若し恁麼ならば、他は是れ目前の法に非ず、耳目の所到に非ずといふとも、一糸毫の礙滞なく見得し、一微塵の異路なく了得すべし。且く如何が弁別して此の因縁に著語することを得ん。
【頌古】
性空内外無く、罪福蹤を留めず。心佛本是の如く、法僧自ら暁聡なり。
※註 古典文章内における歴史的表現につき差別的意図はありませんのでご了承ください
「正法眼蔵諸悪莫作」には、
・・・諸悪すでにつくられずなりゆくところに修行力たちまちに現成す。この現成は盡地盡界、盡時、盡法を量として現成するなり、その量は莫作(実相)を量とせり、正當恁麼時の正賞恁麼人は諸悪つくりぬべきところに住し、往来し、諸悪つくりぬべき緣に對し、諸悪つくる友にまじはるににたりといへども諸悪さらにつくられざるなり、莫作の力量現成するゆゑに、諸悪みづから諸悪と道著せず、諸悪にさだまれる調度なきなり。・・・
とお示しであります。是を実相懺悔と云います。又、宮崎禅師様は「若き佛たちへ」で、「目の前にあるすべてのものは佛様であり、かつ佛様を超越し、佛様を忘れて、佛様を実行している。佛様は佛様であることを忘れて仰のまことを行いつくしている」と述べられています。
先にありました「經豪紗」には、
戒トハ制止ナリ、對治ナリ。制止ト云ハ、釋迦牟尼佛、始テ菩提樹下ニ坐シ、無上正覚成リ終テ、結シ玉フレ戒ヲヲ制止ト名ク、我レ興二大地有情ト一同時成道ト制止スルナリ、故ニ佛戒ト云フ、但先師モ未レ説。諸佛モ未ルレ説戒アリ・・・是レ森羅萬象ノ、自道取也。以二此道取一佛戒受持ノ功徳ト云フ、此ノ外更ニ果ヲ待ツ事不レ可レ有。
とあります。
この「正法眼蔵諸悪莫作」と「梵網経略抄」のお言葉と宮崎禅師様のお言葉が、ぴったりと符号致します。
六道輪廻する姿も見て参りました、六道輪廻から抜け出すには、因縁所生の本来の自己に立ち返れば良いと言うことも見てきました。長い間、自分の思い込み、習慣、廻りの影響によって中々抜け出せない生身の自分も見てきました。
さて、自己と法と戒(律)と禅とは一所のものだと説いてまいりましたが、「この法は人々の分上にゆたかにそなわれり」とありますからそれを信じて実行すれば良い訳ですが、私のような者に法がそなわっている、私が釋迦牟尼佛如来の智慧徳相を具有していると言われでも、にわかには信じ切れないのが、凡夫の凡夫たる由縁ではないでしょうか。ですから高祖様も「正法眼蔵弁道話」に「いまだ修せざるにはあらはれず、證せざるにはうることなし」と言われているのであります。
この法が「人々の分上に豊かにそなわっている」とするならば、高祖様・太祖様はじめ我が曹洞宗の方々のみに具わっているのでしょうか。曹洞宗以外はどうか、外国人はどうかと言う疑問が出てきてあたり前であります。そこで先程の丘任宗潭老師の「少なくとも人間と言えば何人もこの戒を守らずにはおれない、この佛道を踏まねばならない」との慈悲心も生まれて来る訳です。宗教、宗旨、宗派を違えても人間であれば戒、すなわち禅すなわち法を具えている所の証明を事例を挙げながら明らかにして参りたいと思います。これから上げる事例は人間にはいわゆる佛性が具わっているという例であり、当然のことながら仏道に対してそれぞれの浅深があるものと考えております。また、高祖様は五百生の生まれ変わり、釋迦牟尼佛は八千遍の生まれ変わりとも申します。
佛道は職業ではないことの証の一端として、まず、お坊さんにならない時でも仏の世界に気付いた例を橋本禅嚴老師「普勧坐禅儀模壁」から引用してみましょう。
私が坐禅を始めたのは十八才の春で、四十一才の母が僅か一週間ばかりの病臥で急逝してしまった。心配ばかりかけて、只の一度も孝行せずに取り返しのつかぬことになった。その時の後悔と悲しみ深刻な無常観に毎日泣きあかした。この悲しみを忘れたいと、あがいたが何の手がかりも得られなかった。その時突然思い出したのは五年前小学校で先生が座禅のことを一口話したことがあった。然し座禅はどうしてやるものか知らなかった。何か手がかりはないかと探しているうちに普勧座禅儀が見付かった。それから家族の者に気付かれないように工夫しながら皆が寝静まるのを待って坐り始めた。それから三ヶ月程してから身心に変化が現れ、全く予想もしなかった世界のあることを知った。それが一生を坐禅に抛つ動機となった。
これらの体験をもっと分かり易く丁寧に説明した本を見つけましたので長くなりますが読みます。
「悩みぬく意味」
明治大学教授 諸富祥彦
十四歳から二十一歳にかけての7年間、私は、「ほんとうの生き方とは何か」「それが分からないと生きていけない」と、悩み苦しむ毎日を送っていました。しかし、私は、ただ私一人の生き方の問題として、思い悩んでいたのではありません。私の悩み苦しみは、現実の人間への不信感と嫌悪感、そして、人類の精神性を変えなくては、という使命感に由来するものでした。
私の問題は、私個人の問題ではなく、人類全体の問題でもあり、私は人類をその本来の使命に目覚めさせるために、この世に生まれてきたのだ。・・・
私が救われた瞬間
3年、5年、7年・・・。周囲の時間は流れていくのに、私の時間だけは止まったまま。生きることも死ぬことも許されず、ただ観念的な問いだけに支配され尽くした毎日。私は窮地に立たされ、崩壊していきました。
大学3年のある秋の日に、ついに決意したのです。
このままでは、限界だ。
これから3日間、飲まず食わず寝ずで、本気で「答え」を求めよう。そしてそれでもダメだったら、今度こそきっぱり死のう、と。
3日後・・・「答え」は見つかりませんでした。「ああ、これですべて終わった。もうどうにでもなれ」心身ともに疲労の極限に達していた私は、ふと魔が差して、それまで7年間も一人で抱え続け、苦しみ続けたその問いを、突然放り出してしまったのです。
けれども、何ということでしょう。その瞬間、「答え」はやってきたのです。(中略)
するとなぜかそこで、何かに生かされている自分に気がついた。自分が生きているのではない。何か大きな「いのちのはたらき」そのものが生きているのであって、「この私」などは、そのはたらきのごくわずかな断片にすぎないことに気づく。そしてそれに気づくと、「私の悩み」なんてものはあまりにちっぽけで、途端にもうどうでもいいことのように思えてくる。
それでまた「とりあえず、生きてみようか」という気持ちになってくる。そんな体験をお持ちの方は、それなりにいるのです。(中略)
そして、こんなふうにいろいろな方の似たような体験をお聞きしていると、そこにはある種の普遍性が存在するのではないか、私の個人的な体験などではないのではないか、と思えてきました。
それはそうでしょう。私が体験した「真理」は、私が作ったものではなく、あくまで「私を通して現れてきたもの」だからです。
もちろんそれは、私を通して語られ言誼開化されたものである以上、私の色合いを帯びたものになるのは当然です。しかし、それでもやはり、それは「私が」語ったものではありません。「心理」が直接現成し、私を訪れ、私はそれを言語化しただけなのです。その意味で、私はただ、「真理」が現成する「器」であったにすぎません。
それは、あえてたとえれば、仏陀をはじめとした多くの仏教の修行者が、さまざまな相違はありながらも本質的には同じような認識に達したのと同様のことが言えると思うのです。(中略)
先の私の体験の特徴の一つは、「立脚点のシフト」が生じた点にあります。「私は、大いなるものに生かされている」とよく言われますが、これはまだ立脚点が「私(自我)」の側にある表現です。
しかし、先の私の体験では、立脚点のシフト(転換)が生じました。「私」の側から、「私は生かされている」と捉えるのではなくて、「いのちのはたらき」の側から物事をみる
ようになったのです。すると、もはや、「私が生きている」とは言えません。
生きているのは「いのちのはたらき」そのものであって、むしろ逆に、「いのちが、私している」。「いのちのはたらき」がまずあって、それがあちらでは「花」という形、こちらでは「草木」という形、あそこでは「鳥」という形をとっている。その司じ「いのちのはたらき」が、今、ここでは「私」という形をとっている。
私の肉体は死によって消えてしまうけれど、私を私たらしめている「いのちのはたらき」はもともとあり、またいつまでもある。不生不滅の「いのち」が、ある時は「私する」し、ある時は「花する」。またある時は「烏する」。次々と変転万化し、異なる形をとっていく。
そんなふうに見ることができます。
この世界のすべてのものは-立脚点が「いのちのはたらき」の側にシフトするにつれて-「ひとつ」につながっており、「ひとつのいのちのはたらき」を分け合っている、という仕方で「見えてきた」のです。
目の前のこの花のいのち、草木のいのち、そして、あそこであくびをしている猫のいのち、私のいのち・・・これらが、「ひとつの同じいのちのはたらき」の現れとして「見えてきた」のです。(以上、抜粋)
宗教者ではない人が、しかも宗教的な修行形態を経ないでも本質の宗教体験に至ることを納得していただけたと思います。この辺が佛教の元になっているかと思います。私が信じた宗教とか特殊な精神状態になると言うことではない、これ以上遡ることができない普遍的な体験を元としております。
もう少し別の角度、妙好人の角度から見てみましょう。
因幡の源左と言う人がありました。鳥取県気高郡青谷町山根で天保十三年(1842) に生まれ、昭和五年に八十九才で亡くなった。源左さんの転機は父親が急逝したことだった。一緒に稲刈りをしていたとき、急に気分が悪いと言って家に帰りそのまま亡くなった。父親は「おらが死んで淋しけりゃ、親さまを探してすがれ」と言って四十才で亡くなってしまった。源左さんは数えで十八才であった。
「親がなあなってみりや世間は狭いし、さびしいやら悲しいやらで、心がとぼけてしまってやぁ。それから親の遺言を思い出して、どっかでも親さまを探さにゃならんと思って親さま探しにかかってのう」
そして毎日のように念仏法話を聴聞したが安心が得られず三十才になってしまった。その日も朝めし前に牛の餌にする草刈に出かけて、六束の草を作り、三把目を牛の背中に載せたときに「ふいっと分からせてもらった」「世界が広いようになって、ように安気になりましたいな。不思議なことでござんす。なんまんだぶ、なんまんだぶ。」また、源左さんはこんなことも言っている。「こっちゃ死にさえすりやええだ。助ける助けんは親の仕事だけのう。」
生死の問題でも自己を預けている姿が見えてきます。このあたりが他力本願の真髄でしょうか。
又、有名な盤珪禅師は、
この座には、一人も凡夫はござらぬが、若しこの座を立たしゃって、(中略)我が気にいらぬことを、見るか聞くかすれば、早やそれに貪着して顔に血を上げて、身の贔屓故に迷うて、つい佛心を修羅に仕替へまする。その仕替へる時までは不生の佛心で居まして、凡夫ではござらなんだが、一念向うなものに貪着し、つい、ちょろりと凡夫になりまする。」また「一切の迷ひも、かくの如くござって、向うなものに取り合って我身の贔屓故に、佛心を修羅に仕替へて、我が出て迷ひまする。(中略)然らば、仰心の尊い事を決定して知りますれば、決定した日よりして、活佛(いきほとけ)で日を送るといふものでござるわいの。」
と言っています。
先ずは、法を知るのに老若男女、宗教、宗派が無関係のことがご理解できたと思います。だからと言って、宗旨替えを勧めている訳ではありません。
この辺のことは道元禅師様は「正法眼蔵生死」の巻に
「この生死は、すなはち佛の御いのちなり。これをいとひすてんとすれば、すなはち佛の御いのちをうしなはんとするなり。これにとどまりて、生死に著すればこれも佛のいのちをうしなふなり。佛のありさまをとどむるなり。いとふことなく、したふことなき、このときはじめて、佛のこころにいる。ただし心をもてはかることなかれ、ただわが身をも心をもはなちわすれて、佛のいへになげいれて、佛のかたよりおこなわれて、これにしたがひもてゆくとき、ちからをもいれず、こころをもっひやさずひて、生死をはなれ佛となる。」
とお示しです。
私の個人的な感想かもしれませんが、高祖様のご文章は文学的であまりにきれいで、盤珪禅師や源左さんと同じような内容でありながらも、耳にひっかかりにくい、するりと右の耳から左の耳に抜けてしまうような気がします。高祖様は文章に至るまで跡形を残さない。「示庫院文」の文章の品格、高祖様の人品といいますか、人格と言いますか、文章に迄あらわれていると思えるのです。けっして前のお二人をけなしている訳ではありません。私のような粗野な者にはむしろ前者ようないい方をされた方が耳に残るような気がします。
さて少し脱線しますが、浄土真宗の開祖親驚聖人の「南無阿弥陀仏」、つまり他力本願の内容は「自然法爾」と言われています。源左さんが言う所の「親さま=佛の世界=阿弥陀佛の世界」に全てをおまかせすることであると思います。従いまして親鸞聖人、浄土真宗では自分で戒律を守って阿弥陀様の世界に入るという自力が成り立たない。信心の他力こそが浄土の世界への道筋である。親鸞聖人にとりましては戒律がすっかり他力本願の世界に入って、少しも型をとどめない。こう言うことが教理上理解できると思います。
又、法は「洋の東西を問わず」とありますが、印度、中国、日本、又は東南アジアの佛教国はいざしらず、他宗教の圏域まで、佛の世界、無我の世界があるのでしょうか。これがなかなか難しい問題ですが、自我の強い精神風土、一神教を信じている人々は信じているが為に無我の世界に入りにくい。
しかし今、アメリカ大陸、西欧において一神教への疑問、無我への欲求があって、禅を学び佛教を学ぶ人々が増えています。また以前、文化庁長官を務められた、日本ではユング心理学の大家であった河合隼雄先生がある本で東洋の「無我」に始めて気が付いた西洋人はユングであったと述べています。ですからユング心理学は佛教の無我を理解できる関係にありますし、また河合先生は佛教にも大変造詣の深いお方でした。
これで「この法は洋の東西を問わず人人の分上に豊かにそなわれり。」と言うことがご理解していただけたかと思います。
次に、中国の居士ので悟りを開いた例をあげます。
蘇東披(名は軾)
進士及第の地方長官、江西省廬山近く、東林寺の常総(照覚) に参じ、無情説法の話で悟って偈を献じた。
渓聾便是廣長舌、山色豈非ヤ二清浄身ニ一
夜來八萬四千ノ偈、他日如何擧二似セン人ニ一
廬山ハ烟雨、浙江ハ潮、未レ到千般恨不レ消
到得テ還來テ無二別事一廬山ノ烟雨浙江ノ潮
この偈は悟境を詩った偈として特に有名です。
次に「從容録」が出来るきっかけを作った耶律楚材の参禅の様子を上げます。
耶律楚材、湛然居士從源、耶律家(yeli)は遼(契丹國)東丹王突欲の子孫で、遼が金(女真國)に滅ぼされてからは金に仕え、金が蒙古から侵略を受けてからは、首都であった燕京(北京) の從容庵に参禅した。その後成吉思汗に仕え、中央アジアへの遠征前後七年を経て、「從容録」が出来る。
「寓松老人評唱天童覚和尚須古従容庵録」の序文に、
・・・予、既に高松老人に謁して、人跡を杜絶し、家務を屏斥して祁寒大暑と雖も、日として參ぜずといふこと無し、膏を焚きて咎を繼ぎ、寝を廢し餐を忘るる者幾んど三年、誤って法恩を被り、謬って子印に膺る、・・・
とあります。例を挙げれば切りがありませんのでこの辺にしますが、「この法は、人人の分上にゆたかにそなはれり・・・」と言うことがご納得いただけたかと思います。
親驚聖人にとりましては戒律がすっかり他力本願の世界に入ってしまって、少しも型をとどめない。戒が成り立たないことが理解できます。
しかし高祖道元禅師は三帰・三聚・十重禁戒の十六条戒を定められました。どうして十六条戒を定められたのかはわかりません。或いは大乗に非ず、小乗に非ずの十六条戒が適当であったのか、単なる圓頓戒の影響であったのか。
この疑問に向き合うには、高祖様の教授戒文の三帰・三聚浄戒・十重禁戒の参究が必要となってまいりますが、時間の関係上此処までとさせていただいて、三帰・三聚浄戒・十重禁戒の参究は後日にさせていただきます。
出典 曹洞宗師家会「正法」第7号 (平成31年)